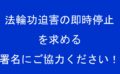米国メディアの記者だったイーサン・ガットマン氏は、中国共産党による法輪功弾圧の始まりを目撃した。他の記者が無関心でいるなか、ただ一人歴史の真相を書き残そうと奮闘した。
独裁政権の監視の目を潜り、情報封鎖を突破しながら調査を続けて十数年。ガットマン氏は、臓器狩り問題は法輪功学習者を用いた実験と大量殺戮に帰結するとの結論に至った。
現在は新著を執筆中とのこと。臓器狩りの問題が収束しない限り、筆を止めることはないと意気込みを見せた。
ーー法輪功迫害の目撃者として、当時の様子をどのように記憶しているか。
私が初めて法輪功学習者と出会ったのは1998年だった。真冬の北京大学で、私は妻とともにアートギャラリーを探していた。クリスマスが過ぎた年末年始はとにかく寒く、凍えそうだった。妻は歩くのが遅いので、私はうんざりして「1、2、3、行進だ」と言わんばかりに闊歩し始めた。
近くの林の中に人々が立っているのに気づいた。誰ひとりとしてコートを着ていなかった。まるで暖かいリビングルームで瞑想しているかのように、ただ立っていたのだ。私はそれを「東洋の神秘」と呼んだ。その後も、彼らが日常的に功法を練習していた北京のメインスタジアムの前で、たびたび彼らを見かけた。そして、中国共産党による弾圧の現場に立ち会うこととなった。
それはとても奇妙な一日だった。まず中南海(中国政府中枢が集まる北京の地名)で一斉検挙があった。その翌日、私が北京のテレビ局で仕事をしていると、法輪功は違法であるとの発表があった。人々は私のオフィスに駆け込んできて、テレビで法輪功について話していると言った。
私は屋外に出た。すると福華大廈の周辺を拡声器を載せたトラックが走り、法輪功は違法だと宣伝した。そして、オフィスにいた何人かの女性が泣き出した。そのうちの一人が「まるで文化大革命の再来だわ」と言った。私はひどく動揺した。当時、私は法輪功について何も知らなかったが、興味を持つようになった。
私は北京にいる多くのジャーナリストを知っていた。彼らは法輪功について何も知らなかったが、知っているふりをしていた。彼らはただ報道を書いていたが、本当に無知だった。そこが重要なポイントだと思った。作家として、人間として、私にできることは、当時の状況を歴史として書き残すことだった。
信仰や宗教について書くつもりは全くなかった。中国という土地で、人々が何を行ったのかをただ記録しようと思った。それこそ問題の真相となるのだ。私の著書『臓器収奪――消える人々』ではもっぱら人々の行動に着目した。私は法輪功学習者の行いをできる限り捉えようと懸命に努力した。
法輪功学習者は私がこれまで会った中で最も立派で、勇気を持っている人たちだ。私は彼らの行いに多くの尊敬の念を抱いている。たとえ私が言葉にしなくても、人々はそのことに気づくだろう。私はただ記録しただけだ。
ーー中国人の反応はどのようなものだったか。
会社におけるただ一人の白人として、その情景を目の当たりにしたのは驚きだった。なかには涙を流している人がいるような感じだった。彼らは学習者ではなかったが、「ああ、またか」という感じだった。その瞬間、私は大きな衝撃を受けた。そのとき、これは中国における最大の問題になるだろうと悟った。そして長い間にわたって、最大の問題であり続けるだろうと。
その後もしばらくは中国と米国を行き来していた。北京の胡同(フートン)にある中国人向けの住宅に宿泊していたときに、警察は何度も私たちのアパートに立ち寄り、色々と部屋を確認した。
他の記者は誰も法輪功迫害について書かなかった。そして彼らは常に距離を置いていた。私が最初の著書を書いた後、法輪功学習者が私にアプローチし、法輪功について本を書いて欲しいと言ってきた。まだ法輪功学習者が中国に残っているのか、会うことはできるのか、と聞くと、女性は「分かった」と答えた。
そして2週間後、彼女は「友人が町に来ている。彼女はあなたと一緒に昼食をとりたいと言っている。彼女は法輪功学習者で、中国のある村の出身だった」と語った。私たちは話をし、長い昼食を取った。私が本を書き始める決心をしたのはその時だった。
ーー中国の国営メディアは法輪功迫害に際して多くのプロパガンダを行った。
当時のジャーナリストらは「新しい中国」が本当に好きだった。彼らはそのことを表立って言わないが、彼らは本当にそれを楽しんでいた。ファシズムや共産主義だったかもしれないが、発展途上の社会であり、楽しかったのだ。西洋人は王様のように扱われた。他の多くの国ではあり得ないのだが、中国では特別扱いされるのだ。
日本や台湾では白人だからといって誰も気にかけない。中国では、一部の人には嫌われるかもしれないが、ほとんどの人には好かれる。それが大きな特徴だった。今やその状況も変化している。五輪の開催を境目に、彼らはドアをバタンと閉め、世界に別れを告げた。今や状況は大きく変化したと思う。
ーー臓器狩りの調査には困難が伴う。どのような信念で取り組んできたのか。
基本的に私は非常に頑固な性格だ。法輪功について本を書いて出版することがダメだと言われるのが嫌いだ。そのように言ってくる人は間違っていると思う。
ときには「臓器摘出というものは、証拠がないのだ」と言われた。すると私は「証拠はある」「もし見つからなかったら、もっと探すまでだ」と答えた。
この活動を通して数多くの素晴らしい人たちと出会い、素晴らしい同僚にも恵まれた。もちろん、臓器狩り問題が未だ未解決ということも理由の一つだ。続編も、さらにその続編も書かなければならない。もちろん逃げ出したい時期もあった。しかし気づけば再びこの問題に取り組んでいた。
ーー新書を上梓するとのことだが、どのような内容になるのか。
『臓器収奪――消える人々』は、何かと悲劇的だ。本当にある程度1作目を読んでいないと、ある意味2作目は読めないだろう。臓器収奪に関する全てがこの一冊にまとめられている。この問題は法輪功学習者を用いた実験と大量殺戮に帰結する。中国の移植産業はすべてこの上に成り立っている。
私は、神に召されたデービット・キルガー氏と、健在のデービット・マタス氏とともに調査を行ってきた。中国で臓器移植が行われているほとんどの病院は、2001年頃までは移植病院ではなかった。しかしある日突然、一般の病院に移植センターが作られた。法輪功学習者という臓器の供給源ができたため、移植ができるようになった。
私にとって、『臓器収奪――消える人々』は全ての始まりだ。続編では、もう少し冒険に関する話や、調査報道の具体的な手法を盛り込みたいと思う。多少なりともエンターテインメント性を持たせよう。
続編のアイデアを出版社に持ち込んだとき、担当者は「これは『臓器収奪――消える人々 第二巻』のようだ」と言った。私は「そうだ」と頷いた。確かに悪くはない。必要となれば『第三巻』でも『第四巻』でも書くつもりだ。私の命がある限り、そして問題が解決するまで、決して筆を止めることはない。
イーサン・ガットマン
中国専門調査ジャーナリスト、共産主義犠牲者記念財団(VOC)上席研究員、中国での臓器移植濫用停止国際ネットワーク(ETAC)共同創設者。著書に『臓器収奪―消える人々』(ワニブックス)、『中国臓器狩り』 (アスペクト、デービッド•マタス、デービッド•キルガーと共著)。
【引用記事】大紀元(2023年3月12日)